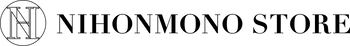【京都府京都市】
末富
1893年に京都で創業の和菓子屋。
京菓子の魅力は味覚だけでなく、色や形から目で、菓子の名前から耳でも楽しめること。
昔ながらの伝統や格式を守りながら革新的な姿勢も忘れず、
魅力的な京菓子を作り続けています。

五感に響く京菓子の素晴らしさを今に伝え、
伝統を守る老舗の和菓子屋です
創業は1893年という老舗の和菓子屋、末富。昔ながらの格式を守りつつも革新的な姿勢を忘れず、心の込もった手作りの和菓子を作り続けています。京菓子の魅力とは味はもちろんのことながら、色や形を目で楽しめ、菓子の名前などを耳でも楽しめることにもあります。さらに、人の情感に訴えるような体験も大きな魅力の1つです。京菓子の遊び心が与えてくれる「夢と楽しさの世界」を込めることが、末富のお菓子作りの原点になっています。伝統を踏まえつつも時代に添ったよいものを取り入れる末富のお菓子は、“京”を感じるお菓子として今も多くの人々を魅了しています。

寺社や茶人にも愛された末富の和菓子は、
日本の文化を支えてきました
初代の末富は、東本願寺の御用達として紋菓などを納めるほか、寺社や茶人のための干菓子や蒸菓子などを作っていました。そして現在でも、東本願寺をはじめ妙心寺、知恩院などの寺社、茶道各御家元との付き合いが続いています。神社仏閣の中心地であり、茶道発祥の地でもある京都で発展を遂げてきた末富は、日本の文化を支えてきた名店なのです。実は、末富のお菓子が一般に浸透したのは戦後のこと。玉子煎餅に、薄くした巨椋池のレンコンや堀川ゴボウ、鞍馬の木の芽などの京野菜を混ぜて焼いた「野菜煎餅」が、大人も好む上品な煎餅として人気を博しました。

昔から親しまれてきた「末富ブルー」の
包装紙は、末富の代名詞の1つです
末富のお菓子は“お使いもの”としても大変人気がありますが、その理由の1つとして、美しい包装紙が挙げられます。透明感と目を引きつける鮮やかさが同居し、洋風ではなく和の趣を感じさせる青色は、「末富ブルー」と呼ばれるこだわりの色目。戦後、末富の2代目が日本画の画伯に新しい包装紙の意匠を依頼し、議論を重ね試行錯誤を繰り返して生み出されたものです。派手過ぎず斬新で、すっきりとした上品な印象を与えるこだわりの包装紙が、末富の和菓子でつながった人々の気分をさらに盛り上げてくれます。

末富 4代目
山口祥二
あらゆることに心を動かし、日本文化の一端を担ってきた京都の地で育まれた京菓子には、粋な遊び心がいっぱいです。末富の和菓子を通じて、京都ならではの「夢と楽しさ」をお届けすることを目指して、今までもこれからも研鑽を積んでいきます。
末富の商品

野菜煎餅・うすべに詰合せ
1893(明治26)年に創業した、京都の和菓子屋「末富」。伝統と革新を融合した“京”を感じるお菓子を生み出す老舗が、代表銘菓2種類を詰め合わせました。寺社や茶人にも愛された京菓子を堪能できます。

京のとき
明治26(1893)年創業以来、多くの寺社や茶人に愛されてきた京都の和菓子屋「末富」。日本文化を支え、今に伝える京菓子を作ってきた老舗で支持され続ける、定番商品の煎餅3種類の詰め合わせです。

光悦 (光悦煎餅・光悦善哉詰合)
日本文化の華とも言える京都の地で、遊び心に満ちた京菓子を作り続ける和菓子屋「末富」。寺社や茶人も御用達の老舗が、江戸時代の美術界の巨匠・本阿弥光悦にちなんだ2種類の和菓子を詰め合わせました。

京ふうせん
遊び心あふれる魅力的な京菓子を通じて、日本文化を今に伝え続ける和菓子屋「末富」。寺社や茶人からも支持される明治創業の老舗が5色の砂糖で京都の季節を表現した、ほのかに甘く軽やかな煎餅菓子です。

酒酵煎餅
五感で楽しむ魅力的な京菓子を通じて日本の誇る歴史や文化を伝え続ける京都の和菓子屋「末富」。寺社や茶人にも愛される老舗の定番商品の1つとして愛される、名酒「十四代」の酒粕入りの麩焼き煎餅です。